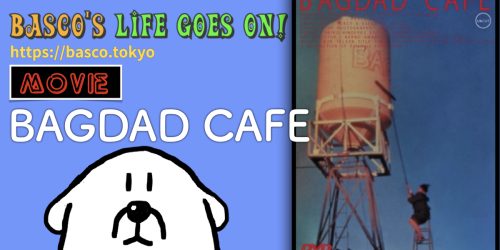俺だけがずっと同じ場所にいたんだね [レボリューション6]

2002年 ドイツ
あらすじ
1984年、まだベルリンの壁があった時代。西ベルリンのマッハノフ通りは無職でジャンキーなアナーキストが跋扈していた。
若き日のティム、フロー、マイク、ネレ、テラー、ホッテは薄汚れたその街で「グループ36」を名乗り政治映画を制作していた。ある日彼らは、打倒資本家を気取って高級ヴィラ地区の無人の屋敷に自作爆弾を仕掛けたが不発に終わった。少々がっかりしたがすぐにそんなことはすっかり忘れてしまった。
時は過ぎ去り、東西ドイツ統一、EU加盟とドイツは目まぐるしくそして大きく変化した。
マッハノフ通りのアナーキスト達もいつの間にかいなくなり、建ち並ぶ朽ち果てたアパートが解体を待っているだけだった。しかしティムとホッテだけは、昔と変わらずアナーキズムを捨てずその朽ち果てたアパートの一室に居座っていた。ホッテは若き日のデモで放水車に轢かれ両足を失い、車椅子生活を送っていた。
そんなある日、長らく無人だった屋敷で爆発事故があり2人が負傷するという事件が発生した。爆発したのは、かつてグループ36が仕掛けたあの爆弾だった。不発のまま放置されていたが、不動産業者が扉を開けたときに爆発したのだった。事件はニュースで大きく取り上げられた。
その事件の直後、別件の捜査でティムとホッテの住むアパートに強制捜査が入り、撮りためていたグループ36時代の政治映画フィルムが大量に押収された。ティムとホッテは焦った。なぜなら押収されたフィルムの中に、グループ36のメンバーが例の屋敷で得意げに爆弾を仕掛ける様子を撮影したものがあったからだ。押収されたフィルムの中からそれを発見されたら、自分たちの犯行であることがバレてしまうことは間違いなかった。
ティムとホッテは、危機に直面していることを知らせるために、ずっと連絡を断っていた元グループ36のメンバー達に会いに行くことにした。
マイクは広告代理店の重役になっていた。
ネレは子沢山の母親として子育てに追われていた。
テラーは弁護士になっていた。
そして、かつてのティムの恋人フローは資産家と婚約していた。
皆、アナーキズムなどすっかり忘れ、社会人としてまともな人生を送っていた。
ティムとホッテからの知らせを受け、皆焦った。事件の犯人が自分達だとバレれば何もかも失うことは明らかだから当然だ。対策を話し合うため、久しぶりに元グループ36のメンバーはかつてのアジト~今のティムとホッテの住まい~に集合した。彼らは話し合いの末、マスコミの取材班に扮して警察内部に潜入してフィルムを奪還することにした。リスキーな計画にビビりながらも、なんとか実行に移すが、目的のフィルムは証拠保管室の頑丈な柵の向こうにあったため残念ながら失敗した。
計画が失敗に終わり意気消沈する彼らだったが、ティムがとんでもないことを提案した。警察の証拠保管室に爆弾を仕掛け、証拠のフィルムを爆破しようというのだ。すぐに賛成したのはホッテだけで、他のメンバーは呆れ返った。しかしいざ材料を集めて爆弾を作り始めると、みんな昔を思い出し夢中になった。ともに作業をするうちにかつての友情が復活したかのような気分になった。
消火器を容器とした手製時限爆弾が完成すると、偽の通報をし、爆弾を入れた木箱を警察が押収するよう仕向けた。計画どおりことは進んだ。しかし、一つだけ計画外の出来事があった。その木箱の中に爆弾だけでなくホッテも入っていたのだ。彼は確実に証拠を隠滅するために、爆弾と一緒に証拠室に潜入し、爆弾をフィルムのそばまで運ぼうと考えたのだ。ホッテは証拠室で木箱から抜け出ると爆弾をフィルムの保管場所まで運んだ。そこまでは良かったが、その直後自力で脱出する術がないことに気づいた。爆発までの時間が刻々と迫る中、ホッテは証拠室の電話を使いかつてのグループ36のメンバーに助けを求めた。警察署に潜入してホッテを救出するのは至難であることは誰にでも分かることだった。しかし、それでも彼らは警察署へ向かうのだった。その結末は……。
感想
なんとなく小綺麗に作られていますが、主人公達はアナーキストつまり活動家です。日本ではなかなか作られないか、作られても共感は得られにくいモチーフでしょうね。
作中で、ビジネスの世界で成功したマイクがティムに対して「なろうと思わないのではなく、なれないんだろう」と指摘するシーンがあります。ティムはそれに対する言葉を持ち合わせていませんでした。政治的活動に限らず、何かしらのムーブメントで中心的存在となった人は好むと好まざるとにかかわらずそのムーブメントのアイコン的存在に祭り上げられてしまうものです。そしてその熱が引き潮のように冷めた後もその人を呪縛し続け、人生のしなやかさを奪い、硬直させてしまう。マイクに問いかけられたティムの心中には、自分がアナーキズムを貫いているのは本当に自己の意志によるものなのか、それとも他人からそうであることを求められていると思い込んでいるだけなのか、そんな疑問が芽生えたのかも知れません。
アイコン的存在となった人物を周りで囃し立てて、熱が冷めるとともに次の波に乗りに行く、節操も信念もありませんし薄情ですが、実際のところ、多くの人の生き方はそんな感じです。私個人としては、こちらの方が人生も気楽だし、精神衛生上もいいんじゃないかと思います。
最初にお話ししたとおり活動家という扱いにくいモチーフではありますが、作品としてはどちらかというとエンターテイメント寄りで悲壮感はありません。ドイツにもこういったムーブメントがあったことを知ることができるという点で興味深い作品です。